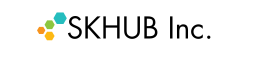減塩より大切!体に良い“本醸造醤油”の見分け方

はじめに
私たちはよく「塩分を控えましょう」「減塩のしょうゆを選びましょう」と言われます。
高血圧やむくみが気になる方にとって、これは確かに大事な視点です。
でも、実はもっと大切なことがあります。
それは「どんな原料で、どんな作り方で、どれくらい時間をかけてつくられた醤油なのか?」ということです。
同じ「しょうゆ」という名前で売られていても、その中身はまったく別物の場合があります。
- 自然の発酵にまかせて、1年以上じっくり熟成させたもの
- 短時間で化学的に味と色をつけたもの
この2つは、香り・コク・体への負担まで違います。
ポイントは、「塩分が少ないかどうか」よりも
「発酵の力でうま味が生まれているか?」
「不必要な添加物が入っていないか?」という視点です。
なぜなら、時間をかけて自然発酵した本物の醤油は、少量でしっかりおいしいからです。
つまり、同じ“しょっぱさ”を感じるために使う量が少なくて済むということ。
結果的に、塩分の摂りすぎも自然と防げます。
この記事では、スーパーでラベルを見るだけで判断できるように、
- 「本醸造」って何?
- 避けたい醤油はどれ?
- 原材料のどこを見ればいい?
- からだにやさしい醤油の選び方は?
を、順番にやさしく解説していきます。
まずは、「醤油ってどんな種類があるの?」から見ていきましょう。
醤油にはいくつか種類があるって知っていましたか?
本醸造(ほんじょうぞう)とは?
本醸造とは、昔ながらのつくり方に近い製法です。
大豆・小麦・食塩を使い、こうじ菌・乳酸菌・酵母といった微生物の力だけで、じっくり発酵・熟成させます。
ポイントは以下の3つです。
- 原料はシンプル(大豆・小麦・食塩)
- 発酵は「生きた菌」の力
- 熟成に時間をかけている
この発酵のあいだに、自然にアミノ酸・有機酸・香り成分・うま味成分が生まれていきます。
いわば「大豆と小麦が、時間をかけて醤油に生まれ変わる」というイメージです。
人間の都合ではなく、微生物の都合に合わせてあげている。
だから味が丸く、香りが豊かで、あと味にイヤな角がありません。
本醸造醤油は、成分が複雑で立体的です。
ごはんや豆腐にちょっと垂らすだけで満足できるのはそのためです。
これが、体にやさしい醤油を選ぶときの基本ラインになります。
「混合」や「アミノ酸液」って書いてある醤油はなにが違うの?
一方、スーパーで安く売られている醤油の一部は、別の作り方をしています。
代表的なのが、「アミノ酸液」や「アミノ酸等」などを原料として使ったタイプです。
これは、大豆のたんぱく質を酸などでいったん分解して、人工的にうま味成分(アミノ酸)を取り出し、そこに甘みや香り
色をあとから足して「醤油っぽい味」にしたものです。
このタイプは発酵に長い時間をかけません。
だから安く、たくさん、早くつくれます。見た目は同じような茶色でも、中身は“醤油風の調味料”に近いことがあります。
こういった製法のものは、原材料名の欄に特徴が出やすいです。
- アミノ酸液
- たんぱく加水分解物
- カラメル色素
- 甘味料
- 調味料(アミノ酸等)
こういった言葉が並んでいたら、自然発酵ではなく「あとから味や色を調整したタイプなんだな」と考えてください。
これは「悪い」「危険」という断定ではありません。
ただ、“本来の発酵が生んだコク”ではなく、“足された味”であるということは知っておきたいポイントです。
ここが、体にいい醤油を選ぶうえでの分かれ道になります。
「再仕込み醤油」「たまり醤油」って健康的?
少しこだわりたい人向けに、聞いたことがあるかもしれません。
再仕込み醤油というのは、普通は「塩水」で仕込むところを、すでにできあがった醤油そのもので二度目の仕込みをするタイプです。
うま味が濃厚で、色も濃い。とろみを感じるほど深いコクがあります。
少量で味が決まるので使いすぎを防ぎやすいのがメリットです。
たまり醤油は、主に大豆を中心に仕込んだ濃い味わいの醤油。
小麦をほとんど使わない製法が多いので、「小麦を控えたい」「グルテンをできるだけ減らしたい」という人にとって
選びやすい場合があります。
この2つも、基本は「本醸造」タイプで選んでください。
つまり、再仕込み醤油やたまり醤油でも、しっかり発酵・熟成させたものと、そうでないものがあります。
見た目が“濃い=良い”ではなく、「どう作ったか?」を確認することが大切です。
原材料の質が健康を左右する
毎日使う醤油だからこそ、どんな原料から作られているかがとても大切です。
「国産丸大豆」や「天然塩」など、原材料の質を見るだけで健康へのやさしさが大きく変わります。
国産丸大豆を選ぶ理由
多くの安価な醤油には、「脱脂加工大豆」という原料が使われています。
これは、大豆から油を搾ったあとに残ったかすを再利用したものです。
コストは安いですが風味や栄養が失われておりうま味の深みが少なくなります。
一方で、「丸大豆」と書かれた醤油は大豆そのものをまるごと使っています。
脂質やアミノ酸が自然に溶け出し、香ばしくコクのある味わいになります。
栄養面でも、ビタミンEやポリフェノールなどの抗酸化成分を多く含みます。
特におすすめなのは「国産丸大豆」表記のあるもの。
国産大豆は遺伝子組み換えの心配が少なく、農薬管理も厳格です。
安心・安全の面でも選ぶ価値があります。
天然塩・天日塩を使った醤油が理想
お米や野菜と同じく、「塩」も大切な原材料です。
一般的な工業塩(精製塩)は、ナトリウムだけを取り出して作られるため、
ミネラルバランスが偏り、味がとがりがちです。
一方、「天日塩」や「海塩」は、カルシウム・マグネシウム・カリウムなどの
微量ミネラルを豊富に含み、体内の水分バランスを整える働きがあります。
ミネラル豊富な塩で作られた醤油は、まろやかな塩味になり、
結果的に減塩しやすくなるというメリットもあります。
パッケージに「天日塩使用」「自然塩使用」と書かれている醤油を選ぶとよいでしょう。
添加物ゼロの醤油を目指す
「保存料」「着色料」「甘味料」「アルコール」などの表示がある場合は注意が必要です。
これらは味を安定させるために使われることが多いですが、
本来の発酵の力で十分においしさを出せる醤油には必要ありません。
特に、「アルコール」は酸化防止として加えられることが多いですが、
香りや味にわずかな刺激を与えることもあります。
できるだけ「原材料:大豆・小麦・食塩」だけのものを選びましょう。
この3つだけで作られた醤油こそ、発酵の力がしっかり生きている証拠です。
原材料を見るときのチェックポイント
実際にスーパーでラベルを見るときは、ここを確認しましょう。
体にやさしい醤油の目安
- 国産丸大豆使用
- 天日塩または海塩使用
- 本醸造の記載がある
- 原材料が「大豆・小麦・食塩」だけ
避けたい表示
- アミノ酸液、たんぱく加水分解物
- カラメル色素、甘味料、調味料(アミノ酸等)
- 保存料、アルコール
熟成と発酵期間にも注目
「発酵食品は体に良い」とよく聞きますが、醤油もまさにその代表格です。
しかし、すべての醤油が自然発酵しているわけではありません。
多くの市販品は、短期間で仕上げるために発酵を人工的にコントロールしています。
本物の醤油を見分けるためには、どれくらいの時間をかけて熟成させたかが重要です。
1年以上熟成させた醤油は「生きている」
昔ながらの本醸造醤油は、仕込みから出荷まで1年以上の時間をかけます。
そのあいだ、こうじ菌・乳酸菌・酵母などがゆっくりと働き、
たんぱく質をアミノ酸に分解しながら、うま味・香り・コクを作り出します。
この過程で自然に生まれるのが、いわゆる“生きたうま味”。
人の手で加えた調味料とは違い、からだにやさしく、奥行きのある味になります。
長期間熟成させた醤油は、香りが深く、あと味が丸いのが特徴です。
一口なめるだけで、まるでダシが入っているような自然のうま味を感じます。
短期熟成・人工発酵との違い
一方で、数週間から数か月で作られる醤油もあります。
これは発酵を早めるために温度を上げたり、アミノ酸液を加えて味を調整したりする方法です。
短期間で仕上げられるためコストは下がりますが、
微生物の自然な働きが十分でないため、味に深みが出にくくなります。
また、人工的に発酵を止めることで保存性を高めているものもあります。
こうした製法の醤油は、発酵食品としての“生きた力”が弱くなってしまうことがあります。
木桶仕込みの醤油に注目
近年、自然派の人々の間で注目されているのが「木桶仕込み」の醤油です。
木桶の中には無数の微生物が住み着いており、
醤油を仕込むたびにその菌たちが自然のバランスを保ちながら働いてくれます。
木桶で仕込まれた醤油は、金属タンクで作るものよりも発酵の種類が豊富で、
うま味・香り・色の層が重なり合う、まろやかな味わいになります。
また、木桶熟成によって生まれる有機酸や抗酸化物質には、
腸内環境を整えるはたらきや、体の酸化を抑える力があるとも言われています。
たとえば、ヤマロク醤油(香川県)や湯浅醤油(和歌山県)など、
昔ながらの木桶仕込みを続ける蔵元の醤油は、少量でも満足度が高く、健康意識の高い方に人気です。
熟成期間を確認するコツ
商品ラベルに「長期熟成」「木桶仕込み」などの表記があればチェックしてみましょう。
中には「三年熟成」など、時間をかけて仕込んだことを明記しているものもあります。
反対に、熟成期間の記載がないものや、「アミノ酸液使用」とある場合は、
短期製造の可能性が高いと考えてよいでしょう。
長い時間をかけて自然発酵させた醤油は、
微生物の力を最大限に活かした“生きた調味料”です。
体にやさしいだけでなく、素材の味を引き出してくれる――
そんな醤油を選ぶことが、日々の食卓をより健康的に変えてくれます。
味と健康の両立──上手な使い方
どんなに良い醤油を選んでも、使い方次第で健康効果は大きく変わります。
「減塩」だけにとらわれず、本物のうま味を生かして少量で満足する工夫を取り入れることが大切です。
塩分を減らすより「質」を選ぶ
減塩醤油は塩分を減らしている代わりに、味のバランスを保つための
「甘味料」や「調味料(アミノ酸等)」が加えられていることがあります。
その結果、自然な発酵由来のうま味が少なくなり、つい量を多く使ってしまう人も少なくありません。
一方で、本醸造のように発酵の力でうま味が生まれている醤油は、
ほんの少しの量でも料理全体の味を引き立ててくれます。
塩分量にとらわれず、うま味の濃さ=満足度の高さで選ぶことが、結果的に健康につながります。
使うタイミングを変えるだけで減塩になる
醤油を「調理中に入れる」よりも、「仕上げにひとさじかける」ほうが香りが立ち、少量で満足できます。
加熱すると香気成分が失われやすいため、火を止めたあとに加えるのが理想です。
たとえば、
- 煮物なら火を止めてから最後に加える
- 焼き魚は焼き上がりに軽く刷毛で塗る
- 冷奴や卵かけごはんは直接かけず、スプレー容器などで霧状に
といった工夫をするだけで、使う量を自然に減らせます。
酸化を防ぐ保存方法も大切
醤油は空気に触れると酸化が進み、風味や色が落ちていきます。
開封後はなるべく早く使い切るのが理想ですが、
長持ちさせたい場合は冷蔵庫で保管し、直射日光を避けましょう。
酸化が進んだ醤油は、ポリフェノールが減少し、
香りが酸っぱく感じられることもあります。
最近は、空気が入りにくい「密封ボトルタイプ」も販売されています。
健康を意識するなら、こうした容器を選ぶのも良い方法です。
醤油の使い方で変わる“料理の質”
体に良い醤油を選び、正しく使うことで、料理そのものの質が上がります。
野菜の甘みや魚のうま味を引き立て、化学調味料に頼らなくても自然な味わいを感じられるようになります。
料理をおいしく、体をやさしく整える。
本醸造醤油は、まさにそんな「調味料以上の存在」です。
健康な食卓のための醤油選び3つのポイント
減塩だけを意識して醤油を選ぶ時代は、もう終わりかもしれません。
これからは「どうやって作られたか」「何が入っているか」「どんなふうに使うか」という視点で、自分と家族の体を守ることが大切です。
ここでは、毎日の買い物で役立つチェックポイントを3つにまとめました。
① 本醸造を選ぶ
醤油はすべて同じではありません。
じっくり発酵・熟成させた「本醸造」の醤油は、微生物の力で自然なうま味が育っています。
これは、アミノ酸などをあとから加えて味をつくったタイプと決定的に違うポイントです。
ラベルに「本醸造」と書かれているか、まず最初に確認しましょう。
迷ったら「本醸造」がスタートライン、という考え方で大丈夫です。
② 原材料がシンプルかを見る
できるだけ原材料が「大豆・小麦・食塩」だけのものを選びます。
理想的なのは「国産丸大豆」「天日塩」「小麦」。
逆に、次のような表記がずらっと並ぶものは避けたい候補です。
「アミノ酸液」「たんぱく加水分解物」「調味料(アミノ酸等)」「甘味料」「カラメル色素」「アルコール」など。
こういったものは“味を整えるために足したもの”であり、
微生物がじっくり作った本来のコクやまろやかさとは別物です。
③ 長期熟成・木桶仕込みは価値がある
醤油は時間が味をつくります。
1年以上かけて熟成した醤油や、木桶で発酵させた醤油は、少量でも深い満足感があります。
これは「塩分を減らす」のとは別のアプローチです。
しっかりした旨みがあるから、結果的にかけすぎ・使いすぎを防げる。
つまり、自然に“実質的な減塩”につながります。
ラベルに「長期熟成」「木桶仕込み」「再仕込み醤油」などの表記があれば、じっくり作られた良い醤油である可能性が高いので、手に取ってみる価値があります。
今日からできる「ラベルの見方」チェックリスト
- 「本醸造」と書いてある?
- 原材料は「大豆/小麦/食塩」だけ?
- 「国産丸大豆」と書いてある?
- 「アミノ酸等」「甘味料」「カラメル色素」が入っていない?
- 「長期熟成」「木桶仕込み」など時間をかけた説明がある?
- 開封後は冷蔵保存と書いてある?(酸化を防げるタイプだと安心)
ひとつでも「これはいいかも」と思える項目があれば、それはあなたと家族の体にやさしい一本の候補です。
まとめ
醤油は「安いから、なんとなく」で選ぶ時代ではありません。
減塩かどうかだけで判断するのも、もう十分ではありません。
これからの基準は、次の3つです。
1)本醸造であること
2)原材料がシンプルであること(大豆・小麦・食塩)
3)時間をかけて発酵・熟成されていること
この3つを満たした醤油は、少量でもきちんとおいしい。
それは、味だけでなく「塩分をかけすぎない暮らし」にもつながります。
醤油は毎日つかうものだから、ほんの少しこだわるだけで、体はちゃんと変わっていきます。
今日からラベルをじっくり見る習慣を、はじめてみましょう。
編集部おすすめ:体にやさしい本醸造醤油 3選
ここでは、この記事でお話ししてきた基準(本醸造・国産丸大豆・添加物に頼らない・長期熟成)に沿って選んだ醤油をご紹介します。
「減塩」ではなく「どう作られているか」「どれだけ少量で満足できるか」という視点で選んでいます。
ご家庭に“まずは1本”というときの参考にしてください。
① 湯浅醤油「蔵匠 樽仕込み」 (和歌山・湯浅)
まず「ちゃんとした醤油を家に置いてみたい」という方におすすめの1本。
刺身・卵かけご飯・冷奴など、生で香りを味わいたい人向けです。
- 本醸造・天然醸造。昔ながらの杉樽でじっくり熟成。
- 500日以上(1年半以上)の長期熟成で、少量でもしっかりコクと香りがある。
- 原材料は「大豆(国産)・小麦(国産)・食塩」だけ。甘味料、カラメル色素、「調味料(アミノ酸等)」などを足していない。
- 塩味がとがらず、あと味が丸いので「かけすぎ」を防ぎやすい。
ポイントは、微生物の発酵だけで旨みをつくっていること。
これはこの記事で何度もお伝えしている「発酵の力で自然なうま味が生まれている醤油」を選ぶ、という考え方そのものです。
② ヤマロク醤油「菊醤(きくびしお)」 (香川・小豆島)
「もう安い醤油には戻れない」というレベルの濃い旨みと香り。
卓上で“最後のひとさし”として使うタイプです。豆腐や刺身のほか、ステーキや焼き野菜の仕上げにも合います。
- 木桶仕込み・天然醸造。蔵に住みついた菌だけで自然発酵。
- 約2年熟成という、時間をかけた深いコク。
- 原材料は「大豆(国産)・小麦(国産)・食塩」だけ。甘味料やカラメル色素などは不使用。
- 旨みが非常に濃いので、むしろ“ちょっとだけ”で満足できる=塩分をむやみに足さなくていい。
この記事で触れてきた「長期熟成」「木桶」「添加物に頼らない」という要素を、そのまま形にしたような1本です。
特に“香りを楽しむ”料理で真価を発揮します。
③ 木桶仕込み・国産丸大豆の「普段づかい用しょうゆ」 (台所の“いつもの1本”を置き換える)
「毎日の煮物や炒め物にも、ちゃんとした醤油を使いたい」という人向け。
いわゆる“木桶仕込み 丸大豆しょうゆ”という表記のタイプです。
- 本醸造であること(ラベルに「本醸造」と書かれている)
- 原材料が「大豆(国産)・小麦(国産)・食塩」だけになっていること
- 国産丸大豆使用と書かれているもの(「脱脂加工大豆」ではなく「丸大豆」)
- 木桶仕込み・長期熟成(1年以上)と説明されているもの
味が濃すぎず、毎日の味付け全般に向いています。
家族みんなの料理にそのまま使えて、しかも「アミノ酸等」「カラメル色素」「甘味料」に頼らない安心感があるのがポイントです。
リンク先は「蔵匠 樽仕込み」720mlの購入ページ例です。
あなたの地域でも、「本醸造」「国産丸大豆」「木桶仕込み」「大豆・小麦・食塩のみ」と書かれた醤油を選べば、同じ考え方の1本が見つかります。
※上記はいずれも「減塩だから良い」のではなく、「本醸造・国産原料・長期熟成・余計な添加物なし」という基準で選んでいます。
ラベルを見て同じ考え方の醤油を選べば、あなたの地域のお店でも同じように良い1本が見つかります。